コミュニケーションを制する!
会議の進行役を任されたとき、よく準備をして当日に臨んだつもりでも、散漫な議論になってしまって上手くまとめきれないことがある。あの時、議論が深まらなかったのはなぜだろう? 意見の対立を上手くさばくには、一体どうすれば良かったのだろう?
また、相手が人間である以上、時にはお互いの立場や感情を考慮せざるを得ない場面もある。そのあたりが、やりとりの難しさに拍車をかけることもある……。
組織の中で仕事をするために、どうしても避けては通れない「コミュニケーション」のリアルな課題について、選書の中からヒントを見つけてみよう。
『ファシリテーションの教科書:組織を活性化させるコミュニケーションとリーダーシップ』
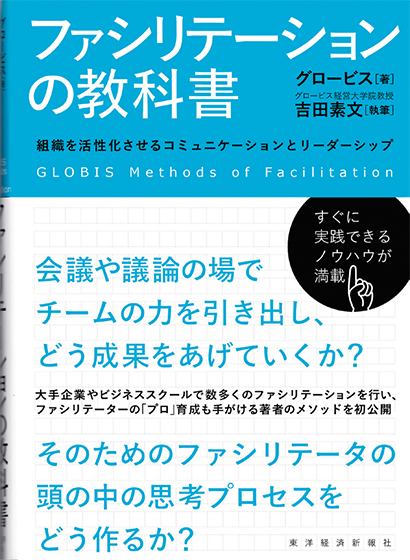
ファシリテーションとは、会議や議論で参加者・チームの意見を引き出し、より良い結果を導き出すためのマネジメント手法のこと。本書では、さまざまな思考法とコミュニケーションを使い、参加者の個々の立場や感情にも留意しながら議論を進めていく手法について、ケース・スタディを交えながら具体的に解説されている。
執筆を担当するのは、グロービスの講師育成に携わり、自身も大手企業やビジネススクールで数多くのファシリテーションを実践してきた吉田素文氏。日々のビジネスシーンで、真に“使える”教科書だ。
「あの人にはリーダーシップがある」というとき、私たちはどこか、リーダーシップとは生まれついての性格や才能のように捉えている節がある。たとえば、「丁寧に説得を重ねても、なかなか相手が納得してくれない」、「部下に、もっと自分で考えて動いて欲しい」。このような“リーダーシップの問題” の解決に必要なスキルのことを、「場数」とか「人徳」とか、実体をつかみにくい、ぼんやりした言葉で表現しがちになっていないだろうか。
問題の本質は表面上のテクニックではなく、「伝え、説得し、動かす」ことを主眼としたコミュニケーションスタイルに起因していることが見えてきます。これを、「引き出し、決めさせ、自ら動くことを助ける」というスタイルに転換することが必要であり、それこそが「ファシリテーションの本質」なのです。(P4)
筆者は、こうした本質を得たファシリテーションの技術について「単なる会議進行の技法ではなく、リーダーの必須スキル」だと断言している。つまり、心強いことに「リーダーシップに必要なスキルは、学び、訓練することができる」ということでもある。
たとえば、うまく議論がまとまらないとき、ファシリテーターはどう介入すべきなのだろうか。本書に記述されているヒントのひとつを例にとって紹介しよう。
「あと何が揃えば決められるのかを決めるために、今後何をどのように進めるか?」を明確にして合意するという「条件つきの合意」は、きわめて有効性が高く、かつ応用範囲が広いものです。単に「決まらないので次回また話し合いましょう」ではなく、「では、決め方を決めましょう」と提案することを常に意識してみてください。(P174より)
議論が本筋から逸れていくときや、たくさんの論点が挙がって収拾がつかないときなどに、「何を決めれば結論が導き出せるか」という道筋を示すのは、議論の全体を俯瞰するファシリテーターの目線からしかできないことだ。この「条件つきの合意」によって、議論を本筋に引き戻し、論点を必要なものだけに絞り、有意義な“次回” に繋げることができる。
無理矢理に結論を出すのでもなく、ファシリテーターの筋書き通りに議論を誘導するのでもない。「引き出し、決めさせ、自ら動くことを助ける」コミュニケーションをとりながら、スモール・ステップの合意形成を重ねていく。なるほど、これならチームの成果にも、また各メンバーの成長にも結びつくだろう。ひとつの理想的なリーダーシップの形である。
基礎から学びたい初学者にも読みやすく、また実践的場面ですぐに活用できるノウハウも収録している本書。まさにリーダー必携の“教科書” だ。
『ドロのかぶり方』
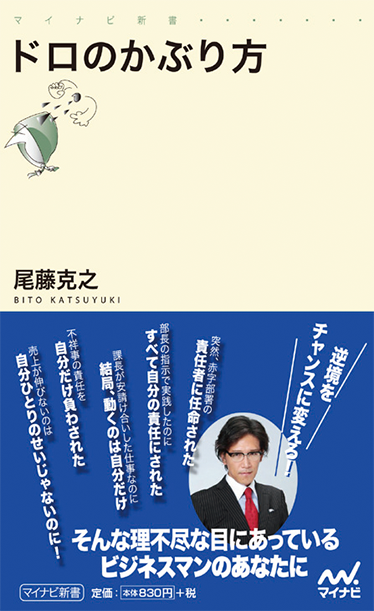
会社員に責任はつきもの。だが、時には「自分の責任じゃないのに……」というケースに見舞われることもある。いわゆる「ドロをかぶらされる」という状況だ。些細なドロならまだいいが、ドロをかぶったがために危機的状況に追い込まれたりしてはたまらない。
元衆議院議員秘書で、大手コンサルタント会社勤務、IT系上場企業役員などを経験した著者は、“理不尽なドロも、上手にかぶれば出世の大チャンスになる!” という。会社員のリアルな現実を乗り切るための「ドロかぶり術」で、逆境をチャンスに変えよう。
一読しただけでも、胃が痛くなるようなタイトルだ。誰だってドロなんかかぶりたくない。だが現実には、誰しも降りかかってくるドロと無縁ではいられない。
ドロかぶりの損得はドロが現れる前に決まっています。(中略)成功したときに出世したり、給与が上がったり、評判が死ぬほど上がるようなドロは大歓迎です。(P23より)
本書中で、筆者は、逆境をチャンスに変えられるドロなら積極的にかぶれと説いている。具体的な例を挙げれば、ピンチの新規事業や赤字部門の責任者、契約を切られてしまいそうな大口顧客の営業窓口、不祥事の後始末役。どれも、なかなかの“貧乏くじ” だ。
だが、ここであえて発想を転換してみよう。これらのドロをかぶらされたとき、ドロを利用して自分の評価を上げたいのなら、「必ずしも大成功を収める必要はない」のである。
本書の中で、「ドロは責任」と筆者は言い換えている。確かに、誰も手を出したがらない赤字事業を黒字転換させることに成功したなら、それはもちろん文句なしのファインプレーだろう。だが、責任の取り方とは「大成功」だけにあらず。赤字事業の行方を見極めて、時には「撤退」を選ぶのも、ドロかぶりの手腕のうちなのだ。ただし、その撤退過程における仕事ぶりこそが、重要な評価のポイントになることを忘れてはならない。
出世する人は、何らかの傷を持っているものです。だから上層部の信用を勝ち取り、上にあげられるわけです。
このような人物は「ドロかぶり」の仕事をよく理解しています。そしてそのことを自覚して、用意周到に手を打ちます。社内への根回しも怠りません。ドロをかぶることを恐れませんし、「たら」「れば」という話もしません。(P191-192)
本書では、ドロかぶりに役立つテクニックも列挙されている。たとえば「ウソの使い方」、「社内の嫌われ者になったとき」、「上司の方針がブレたとき」、「クレーム処理の鉄板パターン」に、「リスク回避の根回し」。どんな読者にも、身に覚えのある項目が見つかるのではないだろうか。本書には、まさに組織で働く人の「リアル」が詰め込まれているのだ。
そう、理不尽なことだが、どうせドロからは逃げられない。それなら「かぶり方」を知っておくのも悪くない。それは、リスクマネジメントの能力と言い換えてもいいだろう。扱い方さえ知っていれば、必要以上にドロかぶりを恐れることはない。
リスクを取れる人材は、ビジネスのあらゆるシーンで「強い」人材である。成果を出すチャンスとして「ドロをかぶる」。そのノウハウ、ぜひ備えとして身に付けておきたい。
『もしアドラーが上司だったら』

大ブームを巻き起こした「アドラー心理学」。ブームに乗り遅れてしまった人にも、いまいちピンと来なかったという人にも、ぜひ気軽に読んでいただきたい。「実用エンターテインメント小説」という形のアドラー心理学実践ストーリー!
ダメダメな営業マン、リョウの前に突如、上司として現れたドラさん。アメリカの大学院でアドラー心理学を修め、抜群に仕事ができて、いつも上機嫌で、時々お寒いギャグを飛ばすドラさんの使命は、部下たちに「働く理由」「仕事の楽しさ」を見つけてもらうこと。ドラさんの「12の教え」を順に読み進めるうちに、日々の仕事、ビジネスにおけるアドラー心理学の役立て方が自然と身についていく、楽しい一冊だ。

 当サイトにつきましては、スマートフォン、タブレットでの閲覧にも対応しております。
当サイトにつきましては、スマートフォン、タブレットでの閲覧にも対応しております。
