~創立70周年~ 社員への思いは一層強く、
さらなる自動化と安全を追求していく
第11回『 自動車用亜鉛めっき鋼板の溶接について』
naeclose 代表・デザイナー 西 紗苗さん
学生フォーミュラ日本大会2025に出展
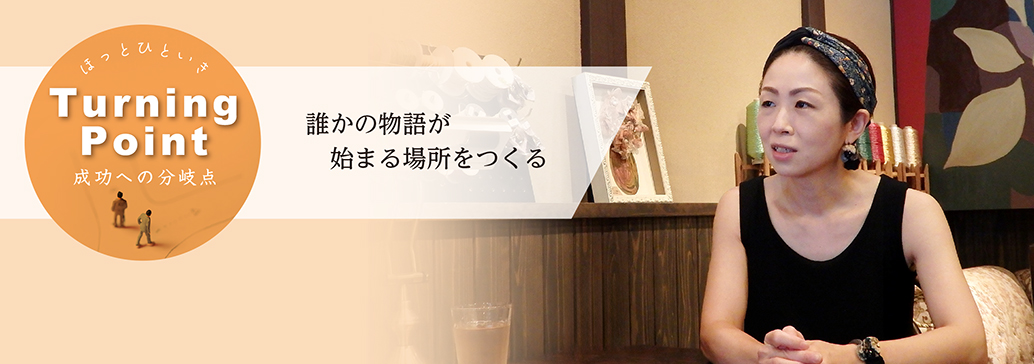
Vol. 03
アクセサリーを入り口にして、
きっかけの扉をひらく
naeclose(ネイクローズ) 代表・デザイナー
西 紗苗さん
- Profile
- 大阪府出身。高校時代からアクセサリー制作を始め、2008年に自身のブランド路面店「naeclose」をオープン。近年は日本のさまざまな工芸素材とのコラボレーションに注力し、数多くの作品を発表している。

「東京中央郵便局(現KITTE)」など、多くのモダニズム建築の名作で知られる建築家・吉田鉄郎。吉田の代表作としては、大正15年(1926年)に竣工した「旧京都中央電話局」もよく知られている。この旧電話局の外観をそのままに“伝統と革新の融合”を体現する商業施設とし生まれ変わったのが「新風館」だ。新風館は2016年に一時閉館し、再開発の後2020年にリニューアルオープンした。この一時閉館の直前、新風館の中庭にはアーティスト・西紗苗さんによるインスタレーションが披露された。直径およそ6m、総重量300kgのワイヤーフラワーオブジェクトである。新風館に捧げられた巨大な花は「新風館」に関わってきた人々がしばしの別れを惜しみ、感謝を伝え、再会を誓いあう場のシンボルとなったのだ。
「アクセサリーでやっていく」と決めた日
まだ高校生だった西さんが、留学先のオーストラリアでアクセサリー作りに出会ったのは1997年のことだった。「自分で作れるんだ」と驚いて、ホストシスターに教わりながら作り始めたのが始まりだ。
西さんは、日本に戻って大学に進学してからも制作を続けた。いつか自分のブランドを立ち上げたいと考えてはいたが、卒業してアパレル業界に就職した後は仕事がとても厳しく、毎日忙しくて目標を実現するための余力を持てないでいた。
そんな時、偶然入ったカフェで「うちに商品を置いてみたら」と声をかけてもらう機会があった。西さんが品物を持って再びお店を訪れると、オーナーご夫妻が揃って出迎えてくれた。初めに小さいバラのアクセサリーを取り出すと、写真家としても活躍していたオーナーは、一瞥して「こんなの誰にでも作れる」と言い放ったという。
「ほかにもあります」。西さんは、そこで引かずに別の作品を出した。アルミワイヤーで造形したハサミのモチーフだった。当時、付き合いのあった美容室の店名入りのオリジナルで、お店に飾ってもらおうと用意したものだ。それを見せると、オーナーの表情が変わった。「これ、すごくいいよ。まだある?面白いのがあれば見せて」。帰り際、オーナーの力強い言葉が西さんの背中を押した。「あなたには個性がある。やっていけるよ」。

ゼロから自由な作品づくりを
その後、西さんは会社を辞めて2006年に独立。2007年には京都市の支援認定を受け、商業施設「新風館」内に1年間の期間限定ワゴンショップを持てることになった。翌年には、京都市街中心部の三条富小路に路面店をオープン。同年内に開業した京都市の店舗の中で、優れたビジネスプランを有する10人のうちのひとりとして選出された。
西さんがアクセサリー作りを始めた1990年代後半から現在に至るまでに、何度かの「ハンドメイドブーム」を経て、アクセサリー用途として数多くのパーツが開発生産されるようになった。今や、手芸店で買ったパーツをパズルのように組み立てるだけで、誰にでも手軽にアクセサリー作りを体験できる。だが西さんが作り始めた当初、手元にあったのはごく限られた種類のパーツと布や糸、金属線、樹脂といった素材だけ。作品づくりは、毎回ゼロからの手探りだった。だが、そこにこそ創造の面白さもあった。
SNSやインターネットでの販売もまだ未整備で、作品を見てもらうのも販売するのも、今よりずっと不便な時代だった。不自由な制作環境で、それでもアーティストたちは自由だった。「とても敵わない、届かないと思わされるような凄みのある作り手がたくさんいた。刺激的で面白かったですね」。そう話す西さん自身も、その環境に懸命に食らい付いて、生き延びてきたひとりだ。naecloseは、今年で創業18年目を迎える。
親しみやすい「工芸の入り口」に
自店舗の経営の傍ら、西さんは定期的に海外へ出向いてクラフトの技術を学ぶとともに、素材を買い付けては持ち帰っていた。一方で、naecloseの本拠地は京都にあるというのに日本の素材のことをよく知らず、使いこなせていないことがずっと気になっていた。
そこで西さんは、当時、京都市からの支援の一環としてnaecloseを担当してくれていた事業コンサルタントに相談してみることにした。コンサルタントの先生が見せてくれたのは、美しい金色の糸巻だった。さらに、これで何か作ってくれる?といって手元に残された糸を贅沢に使い、数点ほど作品を作ったという。実は、これが純金製の高価な金糸で、着物や帯に使われる高級素材だということは後々知らされたことだ。価格を聞いて西さんは震え上がったが、この時作った作品は、そのまま産地である京都府城陽市の商工会議所に納品されることになった。
この仕事がきっかけとなって、2009年以降、西さんは数々の工芸分野とのコラボレーションアクセサリーを発表し、職人たちとの繋がりを深め始めた。たとえば2015年、西さんはアーティストとして初めての個展「kashi」を開催したが、この個展の準備にあたって、西さんが独自に職人らと共同開発した素材がある。京くみひもの内部に金属製のワイヤーで芯を通し、くみひもの外見を損なうことなく自在な曲げ加工を可能にしたもので、商標は「ブレードワイヤー」。これも、伝統工芸の用途を広げる試みの一つだ。
また、最近では老舗の材料問屋、竹田千藏商店のアクセサリーのデザインや組み立てを担当し、錺金具職人の技術を活かした仏教アクセサリー「HOMARE(ほまれ)」立ち上げに企画面から協力している。
「日本の素材も職人さんたちも、本当に素晴らしいんです。これらがアクセサリーという形をとることで、今まで工芸が身近でなかった人にも知ってもらい、親しみを持ってもらえたらと思います。そのためには、naecloseから発信することだけにこだわらなくてもいい。私にお手伝いできることがあるなら光栄なことです」。


始まりの一歩を支える
さらに西さんは、日本の工芸素材の良さを伝えるために、京都を訪れる修学旅行生を対象とした小さなお土産づくりのワークショップを開催し続けている。1時間で金銀糸のブレスレットを作るというもので、ワークショップは、まず金銀糸という素材の説明からスタートするという。高級素材とはいえ、ほんの少量を使う分には価格も抑えられるし、それでいて若い人たちが本物に触れる機会はしっかりと提供できる。
こうした単発のワークショップのほかに、西さんは創業当初から東京、大阪などの都市圏にも定期教室を持って指導を行ってきた。近郊の専門学校でも講師を務め、店舗には毎年、専門学校生のインターン研修も受け入れている。未就学の小さな子どもでも参加できるものから、プロを志向する専門学校生、そして多様な目的の大人向け教室まで幅広い。
「店に長く通ってくれるお客さんや生徒さんはもちろんですが、たとえ1回きりのご縁で、その後お会いすることがなかったとしてもいいんです。ここで体験されたことが、いつか、誰かの次のステップに繋がったらいいなと思って続けています」。
naecloseを通じてアクセサリーを作る楽しさを知ったことや、本物の工芸素材に触れたこと。その経験がその人の中に残り続けて、人生のどこかで輝くことがもしあれば、西さんにとってこんなに嬉しいことはない。
2019年には店舗を移転して、新たな「naeclose」の空間へとリニューアル。新店舗には、カフェ「Café de naeclose」も併設された。「時々、店がみんなの集まる親戚の家みたいになってるんですよ」と西さんは笑う。カフェのお客さん同士で交流が盛り上がることも多く、ここから始まった趣味や仕事の縁が、店の外に飛び出して続いていくこともままある。
「事業をしっかり維持して、この店をずっと続けていくことを今後も大切にしたいです。お客さんや生徒さんがこの場所に集まってくれて、皆さんがここで嬉しそうにしてる顔を見ていられることが、私の幸せでもあると思うから」
かつて西さんの背中を押したのは、嘘や妥協なく誠実に評価してくれる言葉だった。自身がまっすぐ真摯にものづくりに取り組んできたからこそ、今の西さんの仕事ぶりや言葉にも、後進を導く力が宿る。「いろんな人の“きっかけ”をつくりたい」。naecloseもまた、誰かにとっての始まりの場所になろうとしている。



 当サイトにつきましては、
当サイトにつきましては、