四国地区
第10回『SN鋼の溶接材料について』
陶芸家 生駒 啓子さん
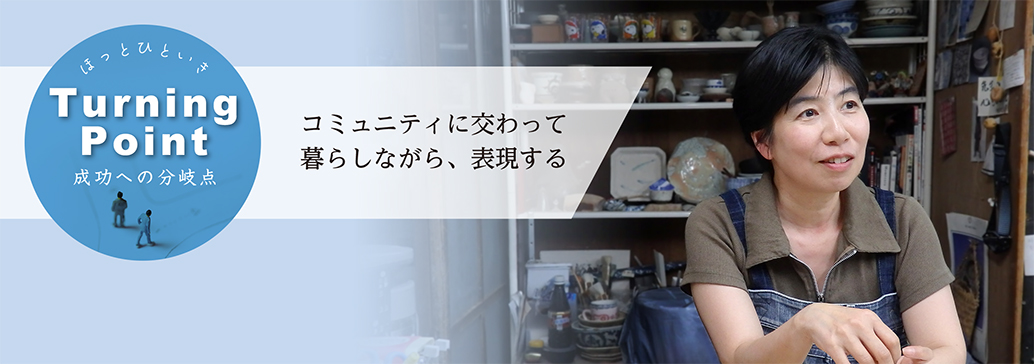
Vol. 02
教えることは学ぶこと。
豊かな学びの円環をつくる
陶芸家
生駒 啓子さん
- Profile
- 大阪府出身。京都精華大学・同大学院で学び、1996年に陶芸家として独立。2003年、京都市立芸術大学博士課程を満期退学。自らの立体造形作品を発表する傍ら、指導者としての経験も長い。

京都西陣、紋屋町。町内に紋織りの技法を発明した西陣織の織屋があったことに由来する地名だ。江戸時代中期には、宮中に収める有職織物を取り仕切った“御寮織物司”と呼ばれた織元六家のうちの五家までが紋屋町内にあったとされる。そのうち三上家は、紋屋町に現存する唯一の紋屋である。
紋屋町の三上家路地は、石畳の路地の正面奥に三上家が位置し、その両脇に棟続きの職人長家が連なる。陶芸家・生駒啓子さんが地元の大阪からこのうちの一軒に移り住んだのは、1996年のことだ。長屋の築年数は、現在およそ150年。歴史ある西陣の町の記憶を繋ぎながら、ここにはいまも、路地に暮らす人々の足音と声が朗らかに響いている。
築150年の京町家を作品制作の拠点に
生駒啓子さんのアトリエ探しは難航していた。大学院在籍中に陶芸の窯を買うお金を貯めて、あとは場所さえあれば独立の準備が整うのだが、いい物件が見つからない。京都の民間団体、町家倶楽部ネットワークについての新聞記事を目にしたのは、ちょうどそんな時だった。
町家倶楽部は、京町家の家主と家を借りたい人との橋渡しを行っていた団体だ。明確な定義はないが、一般的には1950年より以前に建築された木造家屋のことを京町家と呼んでおり、特に京都・西陣地区の京町家の多くは、元々、西陣織の職工たちが働きながら暮らした職住一体型の家である。1990年代当時、こうした町家の多くが廃業などで空き家になっていた。かつて織機を設置していた広い土間は、陶芸の大きな窯を置くにはうってつけだ。
団体の説明会には、数百人もの候補者が詰めかけた。レストランやギャラリーなど事業を目的としたビジネスマンの姿も多く、少し怯みはしたが、生駒さんは、ただの学生だからこそできることもあると考えたという。「私にはお金も実績もないけど、他の候補者よりも時間だけはある。だから自分の足を使って、何度も通って探すことにしたんです」。
町家の借り手は、家賃さえ払えば誰でもいいというわけではない。地縁の強い土地柄で、家主側は、コミュニティに協力的で信頼できる借り手を強く求めていた。生駒さんは、西陣へ何度も通ううちに世話役を務めてくれる町家倶楽部のメンバーと言葉を交わすようになり、次第に親しくなったという。生駒さんが三上家長屋の最初期の入居者に選ばれたのは、そうして築いた人間関係の延長線上での結果だった。
ピークスキルでのエクスチェンジ・プログラム
西陣での制作活動は、同じように京町家で暮らすクリエイター仲間らも含め、刺激的な出会いに恵まれた。
1999年、生駒さんはアメリカ・ニューヨーク州ピークスキル市に滞在することになる。ピークスキルはアーティスト居住区を有し、国内外から積極的にアーティストを誘致している街だ。ニューヨークから西陣へ視察にやってきた都市プランナーが、生駒さんの作品を見て2か月間のエクスチェンジ・プログラムに参加しないかと声をかけてくれたのだ。
そこからは怒涛の勢いで、住む場所と作業場、資材をなんとか手配し、2か月間で制作から作品発表までをやり遂げた。文化や習慣の違いに戸惑うことはあったが、仕事や生活の雑事にペースを乱されず、ただ造形表現に没頭する時間は、日本国内では得がたい貴重なものだったという。英語力が不十分でも目の前に作品さえあれば、言葉の壁を越えて交流できた。当時出会った人たちとの親交は、今も続いているという。
学びたい人の意欲と機会を支える
ピークスキルから帰国した後、生駒さんは京都市立芸術大学の博士課程に進学した。その後は母校でもある京都精華大学で、非常勤講師として18年間もの長きにわたり勤めたほか、現在は京都芸術大学の通信課程で対面授業を受け持つ。また、自身のアトリエでも「生駒啓子陶芸教室」を開き、約20名の生徒と日々作品づくりに向き合っている。
生駒さん自身は、学生時代からずっと昔ながらの師弟関係の中で育ってきた。展覧会に向けて、連日制作に追われる日々だった。師の言葉に黙って従うのが当たり前で、褒められる機会も多くはなかった。いざ自分が教壇に立ってみると、自身の経験と、現在の大学や学生の置かれた環境との違いに戸惑うことも少なくない。少子化やカリキュラムの変化に伴って、教えることの難しさも増しているように感じるという。
一方で、現在の生駒さんの教え子には80歳を過ぎた生徒もいれば、病気や子育てのため学びたいときに学べなかったという人もいる。生徒一人ひとりの背景に触れるたび、再び学ぼうとする意志を支えることに喜びを感じる。
「皆さん、それぞれの人生を持ち寄ってくださって、少しずつ分けてもらっているような気がするんです。技術を教えるだけでなく、人と人との関係が続いていくことが嬉しいですね」。
年に一度の「生駒啓子陶芸教室作品展」は、今秋2025年で開催20回目を迎える。老若男女、動機も背景もさまざまな生徒たちの力作がずらりと並ぶ。当初は生活のために始めた教室だったが、今になって思えば「一人で制作するよりも、日々がずっと充実している」と生駒さんは感じている。一筋縄にはいかないにせよ、それでも、教える仕事はやっぱり面白い。
貪欲に学び、成果をコミュニティに還す
京都精華大学・京都市立芸術大学の卒業生を中心に、生駒さんの師でもある佐藤敏氏から学んだ同門の教え子が集まり、絵付けを学ぶ勉強会「陶画塾」では、年に一度の「陶画塾展」が開催される。
生駒さん自身は、もともと絵付けに苦手意識を持っており、作品に絵を描くことはほとんどなかった。それでも、卒業後に何年も経ってからの「陶画塾」の誘いには「もう一度、佐藤先生の教えを受けられるなら」と迷わず応じ、参加を決めた。

生駒さんの作品「鉄絵花唐草文睡蓮鉢」


忙しい中で通い続けるのは大変だったが「教える立場にある自分こそ、学びをやめてはいけない」という思いが支えになったという。あるときから陶画塾の運営の手伝いを任されるようになったことも、苦手を乗り越えるきっかけのひとつになった。続けていると、楽しさも見えてくるものだ。生駒さんは、佐藤氏が亡くなってからの現在も「陶画塾」で学び続けている。
生駒さんは、元来、学ぶことが好きだ。たとえば金継ぎを学んだのも、はじめは単に、陶芸家として知っておいた方がいいと考えただけのこと。決して使うあてがあって学んだわけではないが、今では金継ぎ、絵付けともに大学で授業を受け持つこともある。2019年には渡米し、現地作家の作品に金継ぎをする機会にも恵まれた。いつどこで何の役に立つのかはわからなくても、それでもいつも、学んで身につけたものが、不思議と生駒さんの進む道を拓いていく。
しかし、家庭のこと、親のこと、自分の健康のこと……、歳を重ねるたびに考えねばならないことは増える。教える仕事の手は抜けないが、造形作家として自身も成果を出さねばならない。
「時間は平等ですから、立ち止まる時間が増えていくのはみんな同じだと思うんです。でも、アメリカで制作をしていると、向こうの人はもっと人生を謳歌している感じがしたかな。彼らはいつから始めても遅くない、何歳からでもアーティストになれると言う。私も、まだまだ納得のいく作品を作りたいし、世界のいろんなところに行って、見たいもの、やってみたいことがたくさんある。欲張りなんですよね」。
学び続け、経験を重ねるたびに、生駒さんのつくる世界は豊かに深みを増していく。


 当サイトにつきましては、
当サイトにつきましては、
